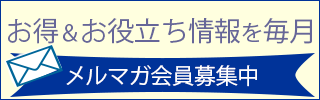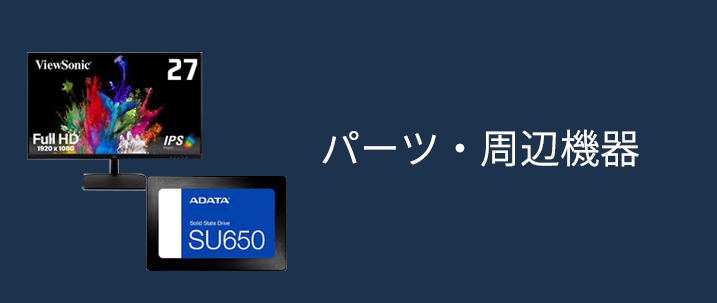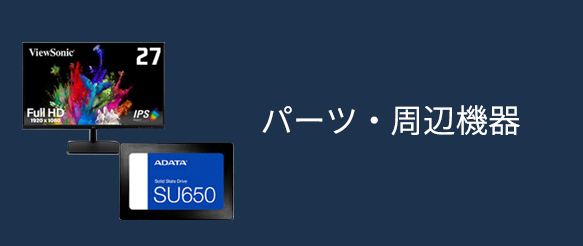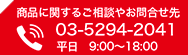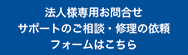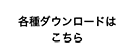- HOME
- 法人様向けお役立ちコンテンツ
- ICT教育とはなにか?メリットと成功へのポイントを紹介
ICT教育とはなにか?メリットと成功へのポイントを紹介

近年、文部科学省が推奨・斡旋するICT教育が主流になりつつあります。一方で「導入するメリットはなにか?」「導入したいが、どのような点に注意して進めればよいかわからない」このような悩みをお持ちの方も、多いのではないでしょうか。
この記事ではICT教育の概要や求められる理由、使われるもの、ICT教育のメリットを解説します。ICT教育を成功につなげるポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
目次
ICT教育とはなにか?
ICT教育とは、情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した教育を指します。一般的には、インターネットを介した学習ツール、パソコン、タブレットといったデジタルデバイスに加え、プロジェクターなどの活用が挙げられます。。ICTを用いた教育では、ICT機器やソフトウェアの扱い方はもちろん、情報の適切な扱い方や適切な発信方法なども合わせて学びます。
ICT教育はさまざまな教科で進められ、教育現場のデジタル化はもちろん、ICTならではの機能を用いた効果的な教育が取り入れられています。ここでは。教科ごとの活用例やGIGAスクール構想との関連、1人1台端末の重要性を確認していきましょう。
ICT教育はさまざまな教科で活用中
ICTは、さまざまな教科で活用されています。文部科学省が公表する活用例を、以下の表でご確認ください。
| 教科 | 活用例 |
| 国語 |
|
| 算数・数学 |
|
| 外国語 |
|
| 社会 |
|
| 理科 |
|
出典:文部科学省「GIGAスクール構想の実現へ(外部リンク)
児童や生徒一人ひとりに対して、1台ずつ端末を用意することの重要性
1人1台端末ではない環境での学校教育では、教員から児童・生徒に対して全員に同じ内容を説明する一方通行の授業であることが一般的です。しかしながら、授業の理解度は、個々の児童・生徒により大きく異なります。限られた授業時間において児童・生徒一人ひとりの理解度に合わせた教育機会を提供することが難しい実態があります。また、児童・生徒同士で多様な意見の共有を行う協働学習では「教室に1台」「グループに1台」端末を導入した場合では、多様な意見を出し合うところまで進めない場合も多いでしょう。
児童・生徒一人ひとりに1台ずつ端末を用意することで、この課題を解決に導けます。教員は授業に対する児童・生徒の反応を、一人ずつ確認することが可能。さらに、個々の学習進度に応じた学習内容を提示することも可能です。加えて、以下に挙げるメリットも得られます。
- 児童・生徒が端末を通して個々の考えを発信・共有することで、多様な意見にすぐ触れられる
- 課題や目的に応じた情報をインターネットを用いて収集し分析することで、調べ学習を主体的に進められる
- 遠隔地や海外にいる専門家・児童・生徒と連携した学習も、スムーズに進められる
1.児童・生徒に対して、情報を主体的に選択し活用する教育が必要
2017年から2018年にかけて、学習指導要領が改訂されました。この改訂では、学習の基盤となる資質・能力に「情報活用能力」が位置づけられました。文部科学省は情報活用能力を、以下のように定義しています。
世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え,情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して問題を発見・解決したり,自分の考えを形成したりしていくための必要な資質・能力
出典:文部科学省「平成30年度文部科学白書 第11章 ICTの活用の推進(外部リンク)」
令和の学校教育では、児童・生徒に対して、情報を主体的に選び活用する能力を養う教育が求められています。これはIT化が進んだ社会を生き抜くために、欠かせない能力です。情報活用能力を育成するためには、パソコンなどのICT機器を用いて情報の選択や活用を能動的に行う教育や授業が欠かせません。
4.過疎化が進む地域でも十分な教育の提供が必要
過疎化が進む地域の学校は、日々の学習や学校運営において、しばしば以下に挙げる課題に直面します。
- 児童・生徒の人数が数名程度となる学校では発想が固定化されやすく、多様な考え方になかなか触れにくい
- グループ学習などを断念せざるを得ない場合がある
- 教員は複数の教科を兼任する場合がある。豊富な知識をもとにした教育を提供しにくい可能性がある
- 専門性の高い人材による指導を受けにくい
地域間格差をなくすためには、これらの地域で学ぶ児童・生徒にも十分な内容の教育を提供することが必要です。ICT教育の活用により、どの地域に住んでいても充実した学びを得ることが可能です。
ICT教育に使われるもの

ICT教育は、さまざまなハードウェアやネットワークを用いて実現されます。それぞれの特徴や使われ方をご確認ください。
パソコン
パソコンは、ICT教育における重要な機器です。文部科学省はGIGAスクール構想の実現において、以下のように「端末の最低スペック基準」を定めています。以下はその一例です。
・OSはWindows Pro/Education相当
・CPUはIntel Celeron Processor N4500と同等以上(Intel社製以外のCPUも可)
・ストレージは64GB以上
・メモリは8GB以上
・画面は10~14インチ、タッチパネル有り
・バッテリ稼働時間は8時間以上
・重さは1.5kg程度を超えないこと
上記のとおり、パソコンのOSはWindows11が要件となっています。児童・生徒がプライベートで使うパソコンもWindows11で揃えると、OSの違いに戸惑うことなく使えます。
もっとも最低スペックのパソコンでは、スムーズに動かない場面があるかもしれません。円滑に学習を進めるためにも、以下に挙げるスペックのパソコンを用意することを推奨します。
| 項目 | 推奨スペック |
| CPU | インテルCorei3~i5 |
| メモリ | 8GB以上 |
| ストレージ | 128GB以上(SSD推奨) |
出典:サードウェーブ「小学生に配布されるパソコンのスペックとは?目的に合ったパソコンを選ぼう!(外部リンク)」
タブレット端末
ICT教育では、タブレット端末を使う場面もあります。文部科学省はiPadについて、「端末の最低スペック基準」を定めています。以下はその一例です。
・OS:iPadOS
・ストレージ:64GB以上
・画面は10~14インチ、タッチパネル有り
・バッテリ稼働時間:8時間以上
・重さ:1.5kg程度を超えないこと
より快適に学習を進めるためには、最低スペックを上回る端末の使用をおすすめします。一例として、「iPad Air(第5世代)」のスペックを以下に示します。
| 項目 | 推奨スペック |
| OS | iPadOS |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| 画面 | 10.9インチ |
| バッテリ駆動時間 | 最大10時間 |
| 重さ | 461グラム |
ネットワーク機器
ICTを用いる学校教育には、ネットワーク機器も欠かせません。ファイアウォールやスイッチは、多くの学校で必要となる機器です。
有線ネットワークの場合は、ハブやLANケーブルも必要です。無線でネットワークを組む場合は、Wi-Fiルーターを用意する必要があります。
高速ネットワーク回線
ICT教育の実現には、高速ネットワーク回線の活用も欠かせません。有線の場合は光回線を使ったインターネット回線の契約、無線の場合は携帯電話会社やWiMAX事業者との契約が必要です。
ICT教育のメリット
ICT教育は、教育にさまざまなメリットをもたらします。代表的な5つのメリットについて解説します。
映像や動画、図表などを活用して、授業をわかりやすく行える
ICT教育では文字だけでなく、図や表、映像や動画の活用も容易です。内容を直感的に把握できるため、児童・生徒の理解度も高まります。
- グラフや地図を重ね合わせて、相違点を理解する
- 条件を変えた場合のグラフの変化を確認する
- 観察や実験を動画で記録し、レポートに写真やグラフを挿入する
- 体験談や事故事例などを動画で視聴する
ICT教育ではこれらの準備がしやすい点も教員にとっての利点でもあります。デバイスがない場合で個別の教材を用いる場合は、事前に印刷しなければなりません。しかしながら、ICT教育なら児童・生徒にデータで提示すればよいため、ファイルの作成にとどまります。
双方向のやり取りを行える
教員と生徒間、生徒間においてコメントや質問を行えることは、ICT教育の代表的なメリットといえるでしょう。児童・生徒は教員に対して不明な点を質問でき、解決しながら授業に臨めるため、児童や生徒自身の学ぶ意欲の向上にもつながります。教員は児童・生徒の理解度を踏まえた授業を行うことで「授業についていけない児童・生徒」を減らし、学力の底上げを実現できます。
また他の児童や生徒の考えを知ることで、異なる意見の存在を認識できます。多角的な視点に基づく深い理解につながることも、メリットの一つです。
個々の理解度に応じて課題を与えられる
一律の授業や課題では、どうしても児童・生徒ごとの理解度に差がついてしまうものです。ICT教育なら個々の児童・生徒の理解度や学習の進捗に応じて、個別最適された課題を提供できます。これにより「できた」という達成感を与えることができ、学ぶ意欲を喚起することが可能になります。
過疎地でも遠隔で、専門の教員による授業を受けられる
過疎地の学校では、すべての教科に精通した教員を揃えることは簡単ではありません。しかしICT教育を積極的に実施するとオンラインで他校の教員や専門知識のある教員による授業を受ける機会を創出できます。地域や教員の不足を問わず一定の教育を担保できることがICT教育を活用する大きなメリットといえるでしょう。
教員の業務負担を軽減できる
教員の業務にかかる負担を軽くできることも、ICT教育を活用する重要なメリットに挙げられます。以下の取り組みと効果は、その一例です。
- 教職員の連絡をオンラインで行うことで、年間で16.7時間を削減
- プリント類をデータで配信することで、年間で43時間を削減
- 家庭学習をオンライン提出することで、年間で33.3時間を削減
- 保護者からの欠席連絡等をオンラインで行うことで、年間で33.3時間を削減
学校は、ICT化が進んでいない職場の一つです。このため簡単なツールの導入でも、大きな業務負担の削減が期待できます。
ICT教育を成功させる5つのポイント

ICT教育を成功に導くためには、押さえておきたい5つのポイントがあります。それぞれの項目を確認のうえ、より良い教育の実現につなげてください。
児童・生徒に対して、十分なスペックの端末を用意する
ICT教育を成果と学力アップにつなげるためには、十分なスペックの端末を用意することが重要です。文部科学省では「GIGAスクール構想の実現 学習者用コンピュータ最低スペック基準(外部リンク)」を定めているものの、この数値はあくまでも最低値です。
快適な学習の実現には、文部科学省が定める基準よりも高いスペックの端末が必要といえるでしょう。ノートパソコンを利用する場合は「16GBのメモリ、500GBのSSDストレージ」など、一定レベルの性能を備えたパソコンを選ぶとよいでしょう。
高速通信可能なネットワーク回線を用意する
ICT教育の実現には、高速通信可能なネットワーク回線の確保も重要です。インターネット回線だけでなく、校内LANも高速通信に対応しなければなりません。
インターネット回線の目安は、文部科学省が「学校のネットワーク改善ガイドブック」で公表しています。児童・生徒の人数によって、推奨帯域が大きく変わることに注意してください。
| 児童・生徒数 | 推奨帯域(Download) |
| 12人 | 22Mbps |
| 120人 | 216Mbps |
| 350人 | 437Mbps |
| 700人 | 580Mbps |
| 1,400人 | 834Mbps |
出典:文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック(外部リンク)」から抜粋
インターネット回線は速度を保証しない「ベストエフォート型」が多いですが、外部要因により突然インターネットの速度が下がり、学習に支障をきたすおそれがあります。コストは高くなりますが、最低速度を保つことが可能な「帯域確保型」や「帯域保証型」のサービスを選ぶとよいでしょう。
高速通信には、校内LANの速度向上も重要です。有線LANの場合は、最大通信速度が10Gbps以上の「カテゴリー6A」以上に対応するLANケーブル、および機器を選ぶとよいでしょう。無線LANの場合は、Wi-Fi 5(IEEE802.11ac)以降の機器を選ぶことがおすすめです。
教員一人ひとりのICTスキルを上げる
ICT教育の実践には、教員が一定レベルのICTスキルを持つことが必須です。まずは学校で扱うソフトウェアやクラウドサービスなどを操作できるレベルをクリアしましょう。オフィスソフトは、よく使われるソフトウェアの例です。そのうえで、ICTの使い方を児童・生徒に教えられるレベルにまで高める必要があります。学習の現場では児童・生徒からICTの扱い方について質問される機会があるためです。
ICTを使わずに教壇に立った経験が長い教員も、ICTスキルの向上に努める取り組みが必要です。教員同士で互いにスキルアップする場を設けることも有効です。文部科学省では「教員のICT活用指導力チェックリスト(外部リンク)」も公表していますので、あわせてご活用ください。
セキュリティを確保する
安心してICT教育を進めるためには、セキュリティの確保も重要です。以下の取り組みを行うとよいでしょう。
- 端末にセキュリティソフトをインストールし、常に有効化する
- 学校のネットワークで、セキュリティに関するシステムを運用する
- セキュリティに関するルールを明文化し、教職員一人ひとりが遵守する
学校にて配布・貸与する端末の場合は、以下の取り組みも有効です。
- 学習に関係ないWebサイトへのアクセスを制限する
- 使えるアプリを限定する
これらは、MDM(モバイルデバイス管理)システムを使うと簡単に行えます。
ICT教育に詳しい事業者に相談する
適切なパソコンやタブレットの選定、適切なネットワークの構築は、専門性の高い技術者によるアドバイスが必要です。「コストがもったいない」という理由で、教職員だけで計画を進めることはおすすめできません。スムーズで安心な学習環境を提供し、学習効果を上げるためにも、ICT教育、ICT導入に詳しい事象者への相談をおすすめします。